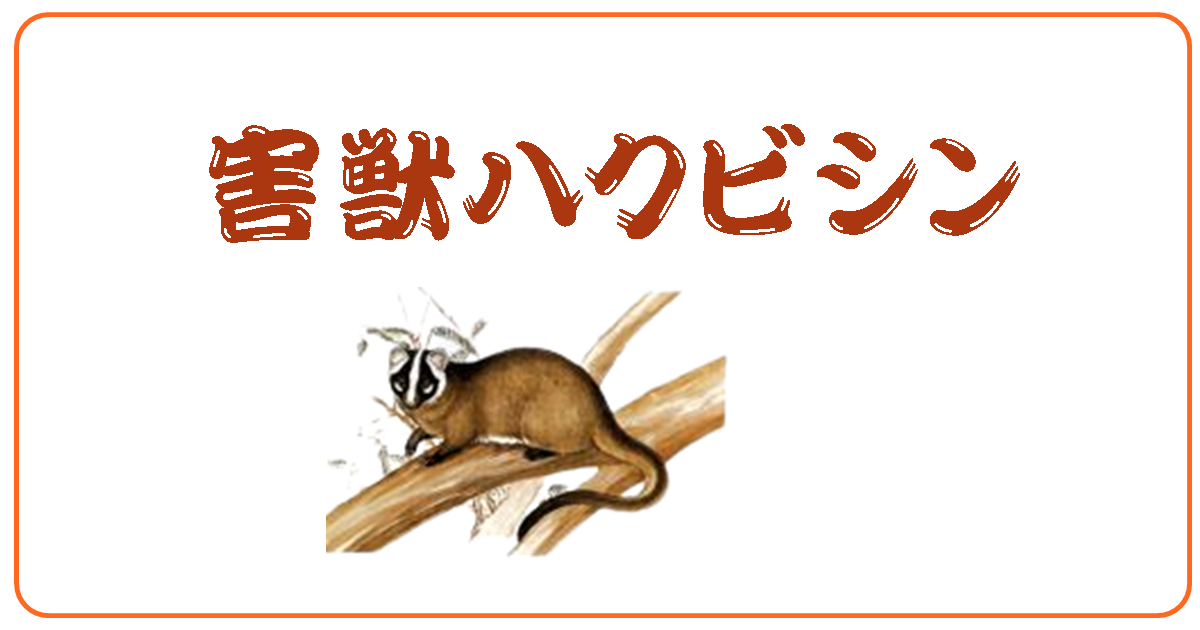ハクビシンは、日本では外来種として定着している動物です。
ハクビシンは、農作物や家禁の被害を与えることがあり、駆除の対象となっています。
しかし、ハクビシンを捕獲するには、都道府県の許可が必要です。
ハクビシンの生態と分布
ハクビシンは、沖縄を除き全国的に生息している哺乳類です。
外国から移入しペットとして飼われていたものが逃げ出して野生化したんですね。
元々、昔から日本に生息していたという説もあるようですが。

ハクビシンの特徴と形態
ハクビシンは、体長、約60㎝、尾の長さは約40㎝で体長の割りには尾が長いですよね。
雌雄、同色で大きさも同じです。
体色は暗灰褐色ですが顔面は黒で、鼻から頭頂部にかけて細い白色の線があります。
それが「白鼻芯 ハクビシン」と呼ばれる所以ですね。
また、四肢の下部と尾の先の方も黒色で体型的には細長です。
ハクビシンの習性
生息地は主に山林などの樹上生活獣ですが、近年では住宅地に出没し屋根裏にねぐらを構えることあるようです。
食性は本来、小動物から果実を採食する雑食性。
しかし、果樹のミカン、柿なども食べ害獣化しているんですね!

出典:狩猟読本
狩猟鳥獣としてのハクビシン
ハクビシンは平成6年に狩猟鳥獣に指定されており、鳥獣保護法に基づいて捕獲することができます。
ハクビシンを捕獲する方法は「狩猟」と「許可捕獲」の2つがあります。
狩猟は銃猟またはわな猟の免許を取得して行う方法で、許可捕獲は都道府県知事に申請して行う方法です。
銃猟またはわな猟にて捕獲する場合は狩猟免許が必要となります。
自宅に出たハクビシンを捕獲する場合は許可捕獲が必要です。
一方、罠でハクビシンを捕獲する場合は使用する猟具として、
・「箱罠」
・「くくり罠」
いずれかの方法となります。
箱罠はハクビシンが入ると扉が閉まる仕掛けで、くくり罠はハクビシンの足を絡めて捕まえる仕掛けです。
ただし、住宅地でくくり罠を使用するのは好ましくありません。
理由は、
・捕獲後の処分(処置)に困る
足だけをくくわれた状態ですから暴れまわります。
・飼い犬や飼い猫がかかる恐れがある。
以上のような理由から、小型の箱ワナを捕獲するのがオススメです。
箱ワナであれば間違ってネコや犬を捕獲してしまっても簡単に開放できます。
また、本来の目的のハクビシンを捕獲できたら、そのまま生きた状態で自治体や業者に処分を依頼できるでしょう。
ハクビシン捕獲後の処置どうする?
ハクビシンを捕獲した後の処理方法については、いくつか重要なポイントがあります。
まず、捕獲したハクビシンの扱いには法律が関連しており、適切な手続きが要求されます。
例えば、捕獲後は他の場所に放すことは禁止されています。
基本的には、捕獲者が責任を持って処分する必要があります。
具体的な処分方法としては、捕殺を行う場合、安楽死などの適切な方法を用いることが推奨されています。
無許可での捕捉や殺害は法律に触れる行為であり、罰則を受ける可能性があります。
また、捕獲後は衛生面にも注意が必要です。
ハクビシンが持つ可能性のある感染症や寄生虫を防ぐため、捕獲した場所や使用した道具の消毒を徹底する必要があります。
さらに、捕獲後の後処理を怠ると、ハクビシンが再び侵入してくることもありますので、清掃や侵入経路の封鎖も忘れずに行うことが重要となります。
捕獲後、具体的な手続きとしては、地域の自治体や専門機関に連絡し、捕獲したことを報告する必要があります。
地域によっては、捕獲後の処理に関する指導が受けられる場合もあります。
また、捕獲したハクビシンを適切に処理した後は、再発防止策を講じることが重要です。
具体的には、餌となるものを外に置かない、食べ物やゴミをきちんと管理するといった工夫が効果的です。
さらに、侵入経路を封鎖することや、ハクビシンが嫌がる匂いを利用して近寄らせない方法も検討すべきです。
まとめ
- ハクビシンの捕獲には、専門的な知識や技術が必要となる場合があります。
- 安全に捕獲・処分を行うために、専門業者に依頼することも検討しましょう。
- 地域によっては、ハクビシンの捕獲に関する規制や支援制度がある場合があります。
-
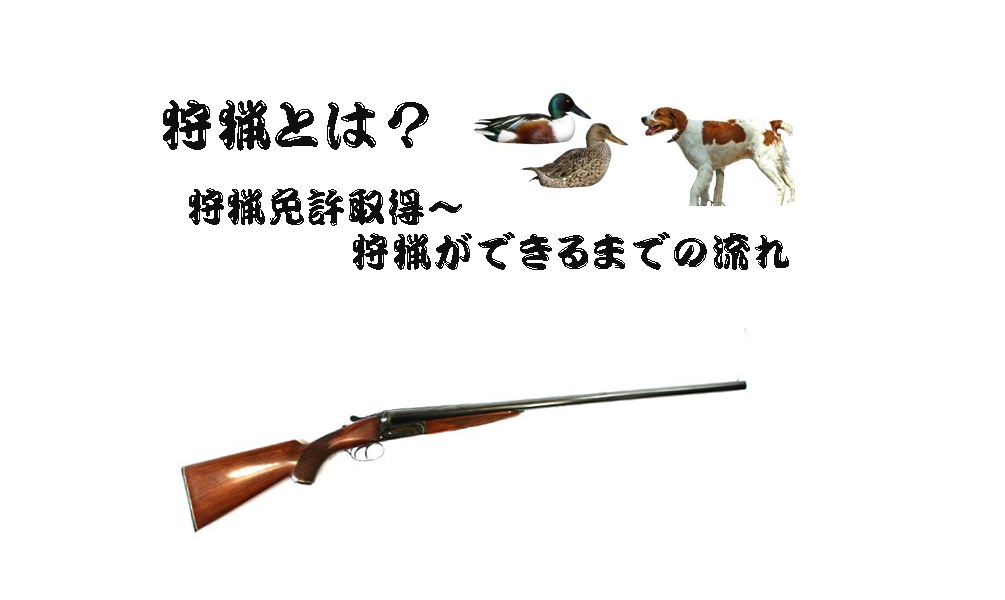
-
狩猟とは?狩猟するには猟具に応じた免許が必要
この記事では、次のことが分かります。 ・狩猟とは ・狩猟免許とは ・狩猟期間 狩猟は、自然を体感しながら獲物をゲットできる楽しみがあります。 また、趣味を超越し野生鳥による農林業への被害削減の役割も担 ...
続きを見る